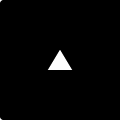菅谷 広宣すがやひろのぶ/経済学部/教授
- 学位
- 商学修士
- 担当科目
- 社会保障論/社会政策/労働経済論/アジア地域研究/英語で学ぶ経済と社会/基礎演習/演習

研究業績:報告書・テキスト・辞典類等を除く(【 】内は判明被引用件数)
単著書
- 『ASEAN諸国の社会保障』日本評論社、2013年8月(全国銀行学術研究振興財団の出版助成採択作)【5】。
共著書
- 『アジア諸国の福祉戦略』(大沢真理編)ミネルヴァ書房、2004年6月(執筆部分:第5章「東南アジアの社会保障:戦略はあるのか?」【5】)。
- 『アジアの社会保障』(広井良典、駒村康平編)東京大学出版会、2003年9月(執筆部分:第7章「インドネシア・フィリピン・タイの社会保障」【13】)。
- 『アジアの労働と生活』(社会政策学会年報第42集)御茶の水書房、1998年6月(執筆部分:共通論題Ⅳ「アジアの発展途上国における社会保障構築への視点」【3】)。
- 『現代世界と福祉国家:国際比較研究』(田中浩編)御茶の水書房、1997年11月(執筆部分「タイ」【1】)。
- 『現代の女性労働と社会政策』(社会政策学会年報第37集)御茶の水書房、1993年6月(執筆部分:自由論題Ⅱ「タイにおける社会保険の形成過程:1932年~1990年」【2】)。
- 『社会保障論』(菅谷章編)日本評論社、1990年7月(執筆部分:第Ⅰ部第4章「アメリカ社会保障法の形成過程」および同第5章「戦後イギリスの社会保障の展開」)。
翻訳書(共訳)
- 白鳥令編『福祉国家の再検討』新評論、2000年3月。
論文(すべて単著)
- "Social Protection and Social Security in Southeast Asia: From the Perspective of the ASEAN Community,"The Journal of Gifu Kyoritsu University, Vol.54, No.1, Oct. 2020.
- (執筆依頼)「シンガポールの医療保障と介護保障」(上)、『健保連海外医療保障』、No.124、健康保険組合連合会(社会保障研究グループ)、2019年12月。
- (執筆依頼)「シンガポールの医療保障と介護保障」(下)、『健保連海外医療保障』、No.125、健康保険組合連合会(社会保障研究グループ)、2020年3月。【1】
- 「日本の財政と社会保障」、『岐阜経済大学論集』第52巻第3号、岐阜経済大学学会、2019年3月。
- (執筆依頼)「UHCの視点からみた東南アジアの医療保障:フィリピンを事例に」、『健保連海外医療保障』No.116、健康保険組合連合会(社会保障研究グループ)、2017年12月。
- (執筆依頼)「タイの医療保障と高齢者介護」、『健保連海外医療保障』No.106、健康保険組合連合会(社会保障研究グループ)、2015年6月。
- (執筆依頼)「インドネシアの医療保障」、『健保連海外医療保障』No.106、健康保険組合連合会(社会保障研究グループ)、2015年6月。
- 「インドネシアの年金・所得保障と貧困削減策」、『賃金と社会保障』No.1634、旬報社、2015年5月。
- (執筆依頼)「インフォーマル・セクターと社会保障:ASEAN3か国の現状と課題」、『社会政策』(社会政策学会誌)第5巻第2号、ミネルヴァ書房、2013年12月。
- 「日本の将来推計人口と労働・社会保障」、『岐阜経済大学論集』第47巻第1号、岐阜経済大学学会、2013年10月。
- 「東南アジア諸国の人口変動:少子高齢化の現状と将来予測」、『岐阜経済大学論集』第46巻第1号、岐阜経済大学学会、2012年10月 。
- 「出生力決定要因に関する研究のレビューと発展途上国への適用可能性:ASEAN4を中心に」、『賃金と社会保障』No.1541、旬報社、2011年7月。
- 「タイの出生率低下に関する考察:世界と東アジアでの位置づけと要因分析、少子化対策、課題と展望」、『賃金と社会保障』No.1536、旬報社、2011年4月【1】。
- 「急速な整備が進むタイの社会保障」、『賃金と社会保障』No.1513、旬報社、2010年5月【1】。
- 「タイの医療保障と地域医療・参加型地域保健活動」、『地域経済』第29集、岐阜経済大学地域経済研究所、2010年3月。
- 「国民皆保険・皆年金を目指すフィリピンの社会保障」、『賃金と社会保障』、No.1501、旬報社、2009年11月。
- 「ASEAN4における社会保障の背景:経済・社会情勢を中心に」、『岐阜経済大学論集』第43巻第1号、岐阜経済大学学会、2009年9月。
- 「マレーシアに社会保障制度は存在するのか」、『賃金と社会保障』No.1496、2009年8月【2】。
- 「改革期に入ったインドネシアの社会保障」、『賃金と社会保障』No.1490、旬報社、2009年5月【3】。
- (執筆依頼)「マレーシアの所得保障と医療保障」、『海外社会保障研究』No.150、国立社会保障・人口問題研究所、2005年3月【7】。
- 「東南アジアの社会保障:制度による類型化を中心に」、『賃金と社会保障』No.1350、旬報社、2003年7月【7】。
- The Establishment of Old Age Pension in Thailand, The Regional Economic Review of Gifu Keizai University No.21, Mar. 2002.
- 「社会保障の補完としての私的保険・企業福祉の諸問題」、『岐阜経済大学論集』第32巻第4号、岐阜経済大学学会、1999年3月。
- (査読付)「導入期のタイ社会保険:1990年の社会保障法(90年法)を中心として」、『早稲田商学』第357号、早稲田商学同攻会、1993年7月【1】。
- 「NHS下のイギリス病院サービス管理政策の変転」、『商経論集』第60号、早稲田大学大学院商学研究科、1991年6月。
- (査読付)「NHS創設とイギリス病院サービス管理政策の発足」『商学研究科紀要』第32号、早稲田大学大学院商学研究科、1991年3月。
研究ノート・評論等(すべて単著)
- (執筆依頼)「シンガポールの老齢時所得保障」、『年金と経済』第33巻第1号、年金シニアプラン総合研究機構、2014年4月。
- (執筆依頼)「マレーシアの老齢所得保障制度」、『年金と経済』第28巻第4号、年金シニアプラン総合研究機構、2010年1月【1】。
- (執筆依頼)「インドネシアの老齢所得保障制度」、『年金と経済』第28巻第4号、年金シニアプラン総合研究機構、2010年1月【3】。
- 「三つの改革で大きな前進を狙う:インドネシア社会保障の最新情勢」、『週刊社会保障』No.2486、法研、2008年6月。
- 「書評 松渓憲雄著『イギリスの医療保障:その展開過程』」、『岐阜経済大学論集』第41巻第2号、岐阜経済大学学会、2008年2月。
- 「国外留学で感じた日本の税・社会保険制度等の矛盾と途上国の社会保障事情」、『地域経済』第20集、岐阜経済大学地域経済研究所、2000年12月【1】。
- (査読付)Review of the Laws and Regulations regarding the Employees' Social Security in Indonesia, The Review of Comparative Social Security Research , No.130, March, 2000.(国立社会保障・人口問題研究所『海外社会保障研究』第130号)【1】
- (執筆依頼)「保険分野における公私の役割分担について」『SWLI』No. 81、静岡ワークライフ研究所、1999年4月。
主要学会報告等(すべて単独)
- (国際学会招待講演:英語)"Social Security and Social Protection: From the Perspective of the ASEAN Community," Cambodian Society for Comparative Laws 9th Annual Conference, Royal University of Law and Economics, Phnom Penh, Cambodia, Feb. 2017.
- (国際セミナー招待講演:英語)Challenges of National Health Insurance (JKN) in Indonesia: A comparative Study with Health Policies in the Philippines and Thailand, International Seminar on Health Insurance, Gadjah Mada University, Jogjakarta Indonesia, Mar. 2015.
- 「タイの少子化問題とその対策」、第121回社会政策学会大会(於:愛媛大学)、2010年10月。
- 「アジアの発展途上国における社会保障構築への視点」、第94回社会政策学会大会(於:千葉大学)、1997年5月。
- 「タイにおける社会保険の生成」、第84回社会政策学会大会(於:昭和女子大学)、1992年5月。
外部資金獲得状況
- 全国銀行学術研究振興財団・研究成果の刊行に対する助成、「ASEAN諸国の社会保障」、2012年度、85万円。
- 生命保険文化センター・生命保険に関する学術研究助成、「タイの社会保険に関する研究」、1991年度、70万円。
以下、報告書・テキスト・辞典類等は省略。
メッセージ
大学時代をいかにして過ごすか。これはとても重要な問題です。大学生活は、良くも悪くも、かなり自由度の高いものですから、4年間(場合によってはそれ以上)がどのようなものになるかは、皆さん次第といってもよいでしょう。もちろん、決められた単位を取得しなければ卒業できないので、これによる拘束はあるし、教員としては皆さんに一生懸命勉強してもらいたい。ただ、なにか一つでも、教室の勉強以外に自分はこれをやったと、後で胸を張れるようなこともやってほしい。社会に出てみればわかることですが、大学時代ほど時間に恵まれたときはありません。その時間を漫然と過ごすのではなく、積極的に色々なことにチャレンジしてほしいのです。
いずれにせよ、充実した大学生活を送ることができる人は、卒業の頃にはより魅力的な人間になっているはずです。そうなるように、みなさんの健闘を祈っています。