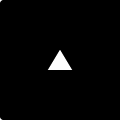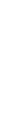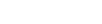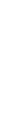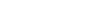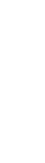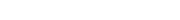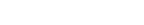会計・税務コース
会計の国際化に対応できる真の会計人を育成
情報通信技術の発展による世界規模での市場単一化に伴った会計情報の国際的標準化が進んでいます。そして、会計基準の国際化に伴う法人税の対応も大きな課題となっています。こうした会計環境の変化の中で、高度な専門性と高潔な倫理観を兼ね備え、地域の発展に貢献できる人材の育成を目指します。
会計・税務コースでは、税理士法第7条に定める「修士の学位等による試験科目免除」制度によって、税理士試験科目の免除を受けることができます。税法に属する科目は「税法演習」、会計学に属する科目は「会計学演習」において、修士論文を作成し、修士の学位を授与された者が試験科目免除の対象となります。
参照:国税庁のサイト
税理士試験科目免除を目指される方へ
修士の学位取得による税理士試験の科目免除制度
修士の学位等取得による試験科目の免除制度については、試験の分野(税法科目、会計学科目)ごとに、いずれか1科目(※注)の試験で基準点を満たした者(いわゆる一部科目合格者)が、自己の修士の学位等取得に係る研究について、国税審議会の認定を受ける制度です。国税審議会から認定を受けた場合には、税法科目であれば残り2科目、会計学科目であれば残り1科目にも合格したものとみなされて試験が免除されます。
(※注)税法科目にあっては、所得税法又は法人税法以外の科目でも構いません。また、試験合格の科目と研究の内容が同一(例えば、所得税法に合格した者が所得税法関係の研究をするなど)であっても構いません。
詳細については、国税庁ホームページ・税理士試験情報をご覧ください。
税法科目または会計学科目免除のための論文指導を行っています
税理士試験に該当する科目(税法または会計学)について、修士論文を作成し、論文審査に合格し修了すれば、税理士試験の該当科目について免除申請が可能となります。
本学では、税法に属する科目は「税法演習」、会計学に属する科目は「会計学演習」において、修士論文を作成し、修士の学位を授与された者が試験科目免除の対象となります。
ただし、免除申請に係る「認定・不認定」は国税審議会によるため、必ず認定されるものではありません。
税法に属する科目の一部免除を希望される場合
税法演習において修士論文を作成

修士論文が国税審議会で認定されることで税理士試験における税法に属する科目の一部(税法科目3科目のうち2科目)を免除
※所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税の試験のいずれか1科目に合格していることが要件
会計学に属する科目の一部免除を希望される場合
会計学演習において修士論文を作成

修士論文が国税審議会で認定されることで税理士試験における会計学に属する科目の一部(会計科目2科目のうち1科目)を免除
※簿記論・財務諸表論のいずれか1科目に合格していることが要件
この制度により税理士資格を取得された方を紹介します。
税理士試験科目免除者体験談
土屋 英次(2013年度修了)

私は30歳手前で営業職から転身し税理士を目指しました。働きながらの税理士試験は予想以上に大変で、3科目合格したときは40歳を越えていました。その後、家族からの後押しもあり、大学院入学を決意し「働きながら通える」「税法の論文が書ける」「家計への負担が少ない」の3つを満たす本学を受験しました。結果としては、先生方の親身な指導、職場や家族の理解もあり、無理なく楽しい学生生活を送ることができました。論文のテーマは仕事に直結する「事業承継税制」とし、実務でも役立っています。また、無事に「税理士試験免除決定通知」を受け取ることができました。今後は、この経験を生かし税理士として成長していきたいと思います。
杉山 真規子(2018年度修了)

私は30歳を過ぎてから簿記を勉強したことをきっかけに税理士を目指すこととなり、30代で4科目に合格しましたが、最後の税法1科目でつまずき、それから17年間税理士になるのをあきらめていました。ところが、あることから岐阜協立大学の修士課程の情報を得ることができ、大学に連絡をしたところ、教務課の方からオリエンテーションのご案内をいただき、参加して教授に会わせていただきました。
教授はじめ学校全体の雰囲気がとても暖かく、すでに多くの税理士試験科目免除者の税理士の先輩方を輩出している実績もあり、すぐに受験を決め、2016年に入学させていただきました。それからの2年間は片道1時間以上の通学時間も全く気にならず、学問を通しての出会いから大切なことを学ぶことができた貴重な時となりました。
2019年3月に税理士登録いたしましたが、大学の研究室が故郷のような気持ちでいつも励まされています。岐阜協立大学での学びを源泉として税理士という仕事を通して社会に貢献できるように頑張ります。
山口 理(2018年度修了)

私は、税理士を志し3科目合格後、長野県の会計事務所へ就職しました。仕事と受験の両立が厳しい中、家庭の事情により時間の確保が難しくなり、本学への受験を決意いたしました。本学では、働きながら通える。地方の学生にも通いやすい。と、新天地を求める私には魅力的な環境でありました。さらに、先生方の豊富な知識、見解を学べる事は実務を昇華する絶好の場であり、とても有意義な学生生活を送れました。論文テーマは我が国の中小企業の課題である「事業承継税制」とし、無事に税理士試験免除決定通知を受け取る事ができました。税務は日々変わり、資格取得後も勉強は続きます。互いに高めあえる恩師や仲間に出逢えた事は今後の税理士業務を行う上で、とても頼もしく、嬉しい事でありました。自分自身も精進を続け、日本経済の発展に尽力して行きたいと思います。
会計・税務コース 科目一覧
| 会計学研究Ⅰ (河合 晋) |
経営分析研究 (梅田 守彦) |
会計学演習Ⅰ・Ⅱ (河合 晋) |
| 会計学研究Ⅱ (河合 晋) |
税務会計研究 (吉田 洋) |
国際会計演習Ⅰ・Ⅱ |
| 財務会計研究 (吉田 洋) |
コンピュータ会計研究 (菱沼 公嗣) |
金融工学研究 (中川 裕司) |
| 国際会計研究Ⅰ (為房 牧) |
税法演習Ⅰ・Ⅱ (石坂 信一郎) |
国際会計研究Ⅱ (為房 牧) |
| 税法研究Ⅰ (石坂 信一郎) |
管理会計研究 (梅田 守彦) |
税法研究Ⅱ (石坂 信一郎) |
演習概要
税法演習
教授 石坂 信一郎

私たちの生活は、税と無関係には成り立ちません。したがって、会計専門職を目指す場合ばかりでなく、租税法の基本原理とは何かを考えることはきわめて重要です。
この演習は、租税法の基本的な考え方を学ぶとともに、現在社会における租税法のあり方を深く考察することを目的としています。具体的な指導内容としては、まず、租税法に関する研究テーマを選定するために、基礎文献の講読を行います。そして、自らが関心を持ち、研究する価値があり、修士論文として完成しうるテーマを決めた後には、専門文献等の収集について指導を行います。その上で、考察の結果を修士論文として結実するための指導を行いたいと考えています。
会計学演習
教授 河合 晋

この演習は、原価計算の理論を理解し、その計算技法の修得を目的とします。企業内外の環境変化に伴い原価計算目的も変化します。その目的から導き出される理論を明確にしながら、原価データや利益データの集計手続を身に付けます。原価計算は、管理会計情報と強く結びつきます。「会計学研究Ⅱ」や「管理会計研究」の学修を踏まえ、自ら関心を持ったテーマを明確にし、修士論文の研究課題を設定します。税理士試験を目指す方は文献研究等を中心に、それ以外の方はフィールドワークや学会報告等を中心に研究活動を行います。その上で、研究した結果を修士論文として仕上げます。
講義概要
会計学研究Ⅰ
河合 晋
企業会計は財務会計と管理会計に大きく分類されます。前者の財務会計は、企業外部の利害関係者に対する会計情報の提供を目的にする会計です。「会計学研究Ⅰ」は財務会計を対象に行い、「財務会計研究」を補完する講義ととらえます。具体的には、日商簿記検定1級(商業簿記)程度の修得を到達目標とし、財務会計に対する理解深化に繋げます。
会計学研究Ⅱ
河合 晋
企業会計は財務会計と管理会計に大きく分類されます。後者の管理会計は、企業内部の経営管理者に対する会計情報の提供を目的にする会計です。「会計学研究Ⅱ」は管理会計を対象に行い、「管理会計研究」を補完する講義ととらえます。具体的には、日商簿記検定1級(工業簿記)程度の修得を到達目標とし、管理会計に対する理解深化に繋げます。
財務会計研究
吉田 洋
財務会計は、複式簿記の手法によって、企業の経営成果と財政状態を測定し、財務諸表を通じて、投資家を中心とする企業の利害関係者に必要な財務情報を提供することを目的とする会計分野です。この講義では、財務会計の基礎である概念と制度のフレームワークを理解するとともに、財務諸表の作成ルール、公開の方法について理解することを目標とします。
国際会計研究Ⅰ
為房 牧
経済のグローバル化によって、各国の会計基準の違いは資金の効率的な流れを阻害するという認識が、国際社会によって共有されるようになりました。国際財務報告基準(IFRS)は、ビジネスパーソン、学生が知っておくべき基礎知識です。本講義ではIFRS全般に関する理解を得ることを目的としています。
国際会計研究Ⅱ
為房 牧
経済のグローバル化によって、各国の会計基準の違いは資金の効率的な流れを阻害するという認識が、国際社会によって共有されるようになりました。国際財務報告基準(IFRS)は、ビジネスパーソン、学生が知っておくべき基礎知識です。本講義では各自の修士論文に沿うテーマを見つけ理解を深めることを目的としています。
管理会計研究
梅田 守彦
設備投資などのような企業の将来を左右する意思決定をおこなう際にも、あるいは実績を計画値に近づけるための統制活動を展開するにあたっても、さまざまなかたちで会計情報は利用されます。この講義では、経営管理に資する会計情報の作成とその利用について考えていく予定です。
経営分析研究
梅田 守彦
この講義の前半では、伝統的ないわゆる財務諸表分析を取り上げていく予定です。そして後半では、近年の株主重視の流れに沿って大きく取り上げられるようになった企業価値(株主価値)の測定方法について検討したいと思います。
税務会計研究
吉田 洋
納税者の権利と義務について理解し、事業を行う個人・法人にとって代表的な税金である「所得税」「法人税」「事業税」の仕組みや企業決算との結びつきを学びます。会計上の利益と税金の計算を特徴づけている確定決算主義について弊害と解決策を検討します。確定決算主義を取っている諸外国の仕組みを理解します。上記の学修を踏まえた上で、各自が問題意識をもって、税務会計に関する研究報告ができることが到達目標です。
コンピュータ会計研究
菱沼 公嗣
コンピュータは、多くの企業において導入されるようになってきており、会計分野においても広く利用されるようになっています。この講義では、コンピュータを利用し会計データを作成するとともに、そのデータに基づく利益計画や業績評価等の会計情報の分析ができることを到達目標とします。なお、受講にあたり、日商簿記3級程度の知識が必要となります。
税法研究Ⅰ
石坂 信一郎
法人税は、株式会社に代表される法人の得た所得を課税標準として課される税で、広義の所得税の一種です。法人税の税収に占める割合は高く、重要な基幹税のひとつです。本講義では、複雑な法人税法の全体像をつかみ、その考え方を理解することを目標とします。基本的文献の輪読によって法人税法の理解を深め、租税に関する幅広い知識を修得できるようにしたいと思っています。
税法研究Ⅱ
石坂 信一郎
法人税は、株式会社に代表される法人の得た所得を課税標準として課される税で、広義の所得税の一種です。法人税の税収に占める割合は高く、重要な基幹税のひとつです。本講義では、複雑な法人税法の全体像をつかみ、その考え方を理解することを目標とします。基本的文献の輪読及び重要判例研究によって法人税法の理解を深めるとともに、租税の時事問題にも触れ、租税に関する幅広い知識を修得できるようにしたいと思っています。
- 役員退職金とその相当性
- 有償ボランティアに対する法人課税の是非
- 船舶リースの損益通算否認
- 売上・減価償却費の未計上と損害額の算定
etc・・・
これらの判例を受講者の中で担当を決め、評釈し発表してもらいます。
金融工学研究
中川 裕司
金融工学は金融商品の価格変動率のリスクやリターン(期待収益率)を分析したり,価格変動率をモデル化して金融商品の理論的価値等を分析し,リスクヘッジやリスクマネジメントに役立たせたり,資産運用の意思決定に役立たせたりすることを研究する学問です。金融工学は1950年代からはじまる比較的新しい研究分野です。研究者の中には数学,物理学といった高度な数学を大学院を修了した人や,膨大な金融データを分析する統計学者などがいます。最近では,金融工学の手法を応用して,油田開発計画やレアメタルの発掘計画などのビジネス計画等に使用されています。内容は受講者の意向に沿います。