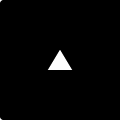「かがやきカレッジ2025」の受講者募集について
岐阜協立大学では、大垣市唯一の4年制大学として、だれでも学ぶことができる生涯学習の場を積極的に提供してまいりました。
今年の「かがやきカレッジ2025」では、7月は本学看護学部教員が、10月は本学経済学部教員が講師を務め、多彩な内容で講座を行います。
皆様のお申込みをお待ちしております!
■日 時
2025年 7月3日~24日、10月2日~23日の木曜日(全8回)
いずれも午後6時~7時30分
■場 所
岐阜協立大学 北方キャンパス
4号館1階・4101教室(大垣市北方町5-50)
■受 講 料
無料(要申込)
■定 員
各講座100人(先着順)
■申 込 先
以下の申込フォームからお申込みください。
https://www.gku.ac.jp/form/-2025.html
|
開催日 |
テーマと概要 |
講 師 |
|
7/3 (木) |
【超高齢社会を支える介護テクノロジーについて】 高齢者の増加と労働人口の減少により、介護人材不足は深刻化しています。そうした中、高齢者ケアを支えるために介護ロボットやICT技術を取り入れる動きが加速していることをご存知でしょうか。どのように介護テクノロジーが導入されているのか最新情報と、活用するメリット・デメリットについてお伝えします。 |
看護学部 講師 吉川 美保 |
|
7/10 (木) |
【がんばらない、上手に頼る介護 ―介護者の立場から―】 超高齢社会が進む中で、誰もが介護と向き合う日がやってきます。在宅介護で生じる家族の負担。この講座では、講師の介護経験をもとに、介護に対する向き合い方やくたびれないためのコツをお話します。現在介護されている方、介護が目前に迫っている方、介護に漠然とした不安を感じている方、老老介護を見守っている娘さんや息子さん等々共に介護について考えてみませんか。 |
看護学部 講師 北村 美恵子 |
|
7/17 (木) |
【体の性と心の性 ―多様な生き方を知る―】 テレビや雑誌で、「ホモ」「おかま」「おねえ」などという代名詞を聞いたことはありませんか。これらの人は笑いの対象や、特別な人だと捉えられがちです。しかし、私たちが持つ体の性別と心の性別、また好きになる性別は全て個性。すべての人が輝いて生きられる社会を目指していきたいものです。 |
看護学部 講師 戸村 佳美 |
|
7/24 (木) |
【高齢者うつ病の理解と予防のコツ】 今、超高齢社会の進展とともに抑うつや頭痛、めまいなどの身体症状が現れる高齢者のうつ病患者が増加しています。また、高齢者のうつ病は認知症と間違われることが多く、正しい知識をもち、早い段階で対応することが大切です。この講座では、高齢者うつ病の症状や原因、認知症との違いやいきいきと過ごすためのコツをご紹介します。 |
看護学部 講師 臼田 成之 |
|
10/2 (木) |
【公務員の「やる気」について考える―公務員は全力で働いて当たり前?-】 近年、国・自治体ともに公務員志望者の減少や早期離職者の増加傾向が著しく、有能な人材の確保や保持は人事政策上の大きな課題となっています。個々の公務員が持っている能力を公務に最大限活かし、やりがいをもって活躍してもらうためにはどのような条件が必要なのでしょうか。近年の行政学等の研究成果から、公務員活躍のためのヒントを探りたいと思います。 |
経済学部 教授 水野 和佳奈 |
|
10/9 (木) |
【『論語』を注釈で読む】 『論語』は長く読み継がれてきた古典ですが、その解釈が分かれている章もあります。『論語』の文章が断片的であるため、さまざまな解釈ができるということもありますが、それぞれの注釈者の思想の問題でもありました。この講座では、いくつかの『論語』の注釈書を資料として使い、それらに句読点や訓点をつける作業を通して『論語』の原文とその注釈との関係を体感していただきたいと思います。 |
経済学部 准教授 杉山 一也 |
|
10/16 (木) |
【ケア労働とジェンダー問題 ―エッセンシャルワーカーの裏側―】 コロナ禍で、人々の暮らしやいのちを守るしごとをしているエッセンシャル・ワーカーのひとつとして注目を浴びたケア労働者。しかし、その待遇は必ずしも十分なものではなく、他産業平均と比較してもかなり低い状況にとどまっています。そこには、ケア労働にまつわるジェンダーの問題が横たわっています。本講座では、その背景に迫ります。 |
経済学部 教授 髙木 博史 |
|
10/23 (木) |
【ひきこもる若者を理解する ―閉ざす若者へのかかわり方―】 ひきこもる若者(15歳から39歳)は、内閣府の調査(2023年3月発表)によれば2.05%(推計65.3万人/2022年10月時点)に及びます。このように地域に共に暮らす若者のうち何人かがひきこもっています。私たちは、ひきこもる若者を理解していくことがまず大切になります。ひきこもる若者への理解と、家族などの当事者へのかかわり方を考えていきます。 |
経済学部 教授 山田 武司 |